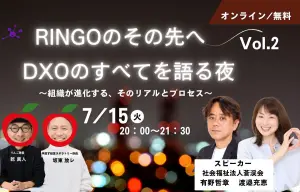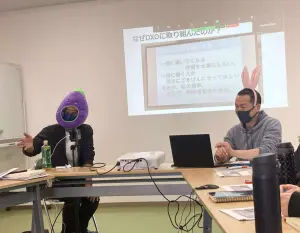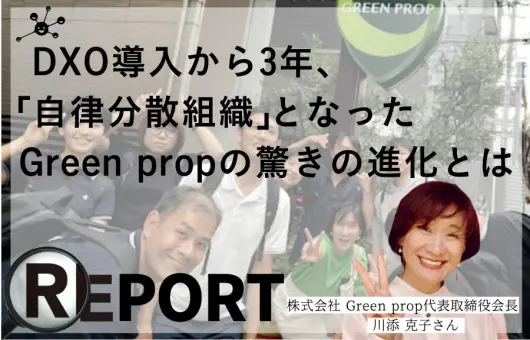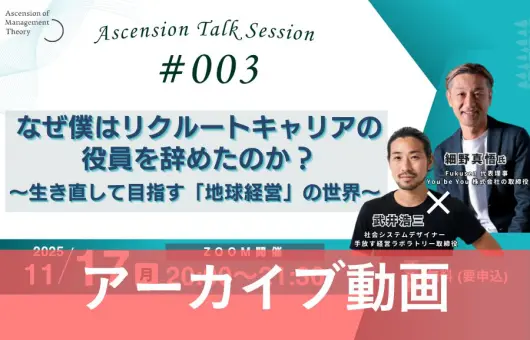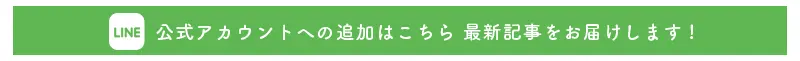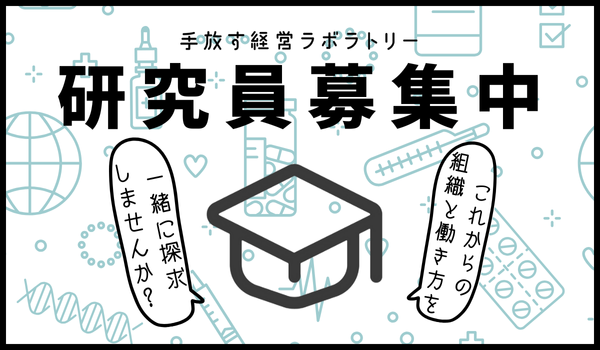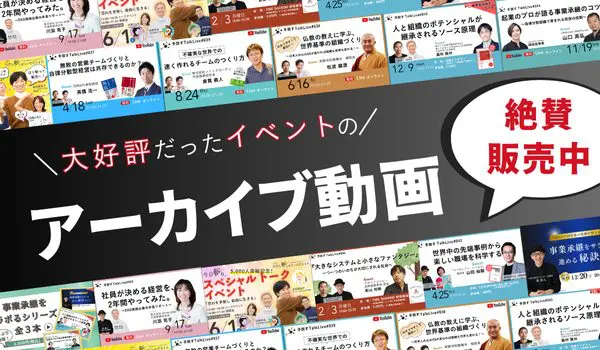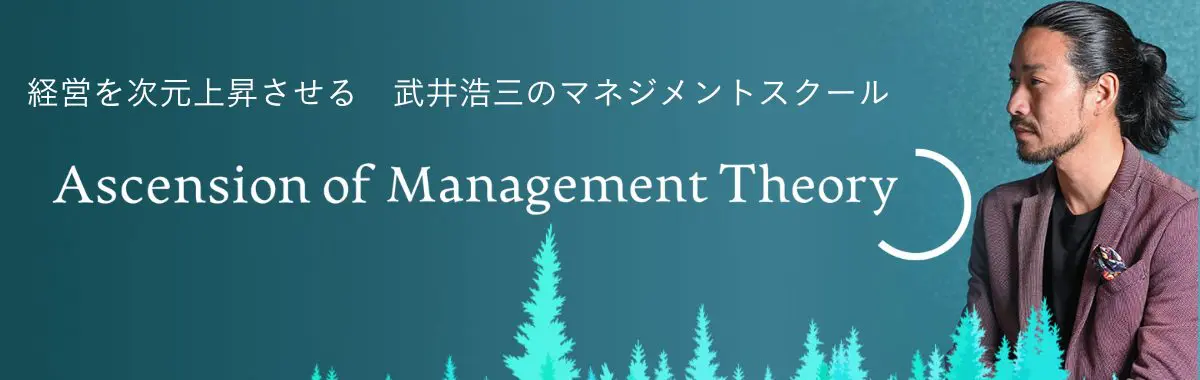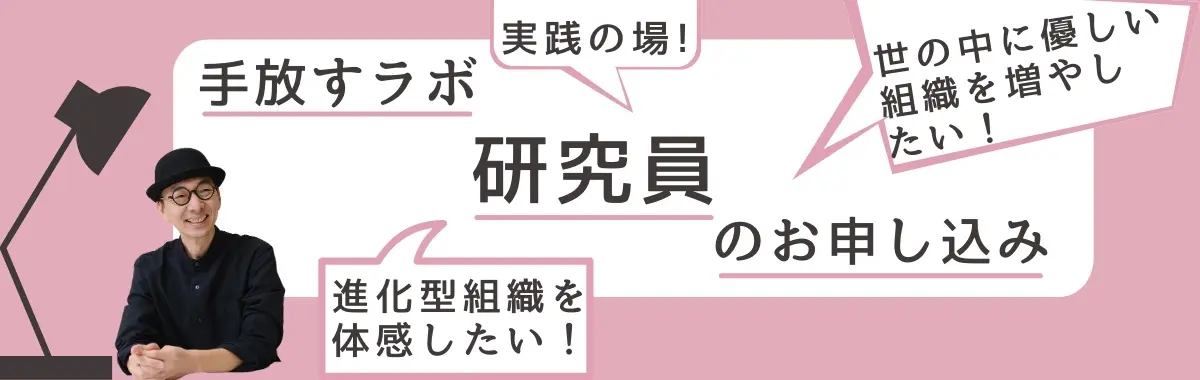2025年7月15日実施「DXOのすべてを語る夜」トークイベント
蒼渓会は、今年2025年で設立29年を迎えられた社会福祉法人。
山梨県南アルプス市の自然豊かな環境で、有野理事長は2代目経営者・渡邉さんは職員(施設長)として、精神に障害のある方々の暮らしを支え、今も延べ500人以上の方をサポートし共に歩まれています。
日本の社会福祉法人として、初めてDXOを導入し、自律分散型スタイルでの運営をしている蒼渓会さん。
それは、理事長の有野さんが「スタッフ一人ひとりが自分らしく幸せに働ける組織にしたい」と願ってのことでした。
「けれども今、誰よりも豊かさを感じているのは、経営者である私自身かもしれません」と語る有野理事長の、数々の涙と今も続いている皆さんの挑戦についてインタビューしました!

社会福祉法人蒼渓会 有野哲章 理事長
社会福祉法人蒼溪会の2代目の経営者。
埼玉県で13年ほど、精神保健福祉センターや精神医療センター、保健所等で公務員として働いた後、平成27年から、生まれ育った山梨県に戻り、社会福祉法人蒼溪会に転職し、現在理事長を務める。
スタッフ一人ひとりが自分らしく幸せに働けるようにと願い、日本の社会福祉法人としてはおそらく初めて、DXOを導入し、自律分散型スタイルで組織運営している。
社会福祉法人蒼渓会 渡邉充恵 職員(施設長)
社会福祉法人蒼溪会で宿泊型自立訓練施設「ボヤージュ」の施設長兼相談支援センター「カマラド」で主任相談支援専門員をしている。
精神保健福祉士として、精神科の医療法人で勤務をしながら、2児を出産。その後「経営のしがらみがない環境で、精神障害者の退院支援をしたい」と願いから、約10年前に蒼溪会へ。DXO体験会で「内在する心の声を大切に仕事をして良い」という、自分を取り戻すような感覚に感動して以降、蒼溪会DXO導入に参画し、現在は自法人のDXO見守りやインストーラーとしても活動している。
福祉で大切にしてきたことに通じる「ティール組織」との出会い
坂東: まず、お伺いしたいのですが、社会福祉法人である蒼渓会がDXOの導入を検討されたきっかけは何だったのでしょうか?
有野: きっかけは2021年に武井浩三さんと出会ったことです。
私は精神保健福祉士の資格を持ち、主に精神に障害がある方の支援をしているのですが、社会からの誤解や差別の中で生きづらさを感じている利用者さんをサポートする中で、「人によって傷つけられても、また人によって勇気づけられて元気になっていく姿を見るのが、この仕事の尊さだ」と感じていました。
武井さんの話を聞く中で、「ティール組織」という概念に初めて出会い、上司と部下の関係がないこと、指示命令がなくても社員が動くこと、対話を大切にすること、そして「土壌のワーク」や「助言プロセス」といったプログラムに強く惹かれました。なぜなら、私が福祉で大切にしてきた「対等性」「当事者性」「自立」「信頼関係」「意志決定」「本人中心」といった価値観が、DXOの想いとめちゃくちゃ一致していたからなんです。
この価値観を、「利用者さんだけでなく、職員同士の間でも大切にしながら組織を作っていきたい」と思い、導入を決めました。
「自分でやれちゃうんじゃない?」
坂東: DXOの導入はすぐ決断されたんですか?
有野:武井さんとの出会いからすぐ2021年12月に、まず私を含めた法人の職員3人とDXOワークショップ体験会(DXOのプログラムはワークショップを中心に進められる)に参加しました。正直なところ、最初は私も講師の経験などもあるので、「自分たちで学んでテキストを使えば、インストーラー(DXOの導入をサポートするファシリテーター)に来てもらわなくてもできるんじゃないか」という感覚があったんです。
でも、実際に体験会に参加してみたら、「これはダメだ」と痛感しました。私がファシリテーターになると、職員が本音で話せなくなってしまう、と。職員に本音で話してもらいたいという気持ちがあったので、2022年9月にDXOの導入(インストーラーのサポートを受けながら)を正式に決めました。
「仲間をバカにするな!」コンサルの言葉で奮起するも・・・
坂東: 導入された後、何か困難なことはありましたか?
有野:実は、導入を決める前、福祉のコンサルタントに「こんな組織を作りたい」と相談したら、「意識が高い人たちが集まってやることだから無理ですよ」と言われてカチンと来たんです。
山梨の田舎の法人で、意識が高い人ばかりが集まるわけではない。それに何より、「一緒に働いている仲間をバカにするな!」と思いました。
そんな気持ちを抱えながらDXOを導入したのですが、蓋を開けてみたら「シーズン1(※導入6ヶ月プログラム)」が終わってから職員が沢山辞めてしまいました
辞めていく職員の中には「自律分散ということは、要は責任も分散するわけだから、お前は責任を取りたくないのだろう」とか、「私利私欲を肥やしたいのか」といった意見も出ましたね。
正直、中途半端な形で「シーズン1」を終えたと感じました。一部の事業所を閉じようかとも悩みました。
渡邉: 私から見ると、元々、組織の中に色々な感情や意見があったけれど、それが表に出ていなかったものが、DXOによって「言っていいんだ」「出していいんだ」という場になった時に、辞めるという決断をする人が出てきたのかなと感じています。
私はそんなに不思議なことが起きているという感じではなく、「やっぱりそうだよね」とどこか納得している自分もいました。
経理担当の職員が何人か辞めたのですが、それはお金の仕組みが整理されたことで、自分の役割がなくなってしまうことへの恐れだったと理解しています。
有野: 職員がたくさん辞めていった時も、DXOが悪いとは全然思わなくて、自分が経営者として未熟だからこういう現実が起きているんだろうとずっと思っていました。
その後採用活動も頑張って、なんとか体制が整ったので、2023年9月から「シーズン2(導入後フォローアッププログラム:MORIフロー)」としてぬいさん(乾:DXOインストーラー)たちに来てもらい、再スタートを切りました。
離職の痛みを越えて、再起動!
坂東: その時、どんな思いで再スタートを切られたのですか?
有野: 「一緒に働く仲間が幸せに働いて欲しい」という願いは、ずっとありました。それだけを信じて、最後までやり切ったという感じです。自分が大事にしたいことを、誰かの理由で辞めることは絶対にしたくない、そう思って再起動式を迎えました。
シーズン1の後、辛くて自分はダメだと責めて泣いてばかりだったのですが、再起動式(組織のOSを新しく切り替えることを確認する、DXOプログラムのイベント)の2日前の2024年9月10日にぬいさんに電話して、「こんな幸せな感じになっていいんですかね?」とまた泣いてしまったんです。
幸せになることに対しても涙が出ていたのがその時の気持ちでした。
70代職員も「使いこなせるか不安」でも情報を透明化
坂東: DXO導入後、蒼渓会にはどのような具体的な変化がありましたか?
有野:情報共有は、情報の透明性を保つためにLINEWORKSからSlackに変更しました。
Slackに変えてから、スタッフのメッセージ量が格段に増え、リアルタイムでの動きが便利だと感じています。今ではSlackがなかったら仕事が無理だと感じるほどです。
利用者さんの個人情報については、フルネームや生年月日、住所はSlackに入れないなど、厳密に取り扱うルールを設けました。
職員の中には70歳を超えるメンバーもいるので、Slack導入には抵抗があったのですが、若い職員が丁寧に使い方を教えてくれ、「この人たちが使えないから諦めよう」ではなく、「分からない人に分かる人が教える」という繋がりも改めて実感できました。
渡邉:Slack導入は、連携のスピード感が格段に上がったことで、利用者さんへの支援も迅速に行えるようになったと感じています。
採用もお金も自分たちで
有野:他にも、これまでは理事長の私が面接に立ち会って判断していましたが、みんさん(渡邉)をはじめ現場の管理者やスタッフに採用するかどうかの決定権もすべて委ねました。
そうするとDXO導入後、これまでたくさんあった「スタッフを増やして欲しい」という各部署からの要望が全くなくなったんです!
皆がお金、特に人件費がどれくらいかかっているかを知ったからだと思うのですが、自分たちでどう回せばいいかを考えるようになったからだと思います。
渡邉:採用の決定権が現場に移ったため、「自分たちが迎える職員は自分たちで決める」という責任感から、採用活動に真剣に取り組むようになりました。
今では私が、有野さんより面接官として厳しいと言われるほどです(笑)。
「海を見ながらお寿司!」の実現
有野:お金の仕組みも「事業活動推進費」の仕組みを取り入れ、 前期の法人全体の利益額の25%を「総事業活動推進費」に充て、各事業所に分配しています。
これは、各事業所のメンバーが「自分がやりたい」という気持ちが湧いてきた時に使えるお金の範囲としています。
福祉事業は法律で人員配置が定められているため、単純な利益額で配分すると不公平になるため、人件費を含まず計算する独自の計算式を導入しました。
この仕組みは、無駄な経費を使うと翌年度の予算枠が減り、利用者さんの満足度に繋がる活動をすれば翌年度の予算枠が大きくなるように設計されています。導入前は職員がお金を扱うことはありませんでしたが、これにより、各事業所がコスト意識を持ってお金を「運用していく意識」を持つようになりました。
実際に先日、1人の職員の発案で「海を見ながら利用者さんと美味しいお寿司を食べたい」という想いを叶えるため、この事業推進費を使って、メンバーとスタッフで観光バスで海の見える静岡県清水へ行ったというエピソードがあります。
実はこの案についてRINGOプロセス(DXOにおける意志決定の仕組み。意志を持った人が提案し周囲から、意見をもらって、最終的に自分が決める)で話し合っていた段階では「山梨でもお寿司は食べられるじゃないか」という意見もあったんです。なので提案してくれた職員はよく考えていたし、迷ってもいました。
その分、事前に現地に自ら休日に足を運んでルートを確認したり、みんなが安全にどうやって楽しめるかを良く検討した上で、やっぱりお寿司を食べるなら海を見ながらだ!と、利用者さんが喜ぶことをしたいという思いで提案したことを実行してくれていました。
渡邉:入職2日目のスタッフが、事業所の収支や事業活動推進費の話を聞いて「こんなお金の話、入って2日目で聞いちゃっていいんですか!?信頼されてる感じがする」と言ってくれたのも印象的でしたね。
有野:他にも、DXOを体験したことで、多くの偶発的な出会いがありました。他の素敵な経営者の方々と情報交換ができたり、法人内で研修を受けたり、様々な繋がりが生まれ、豊さが増したと感じています。
偶発的な出会いから生まれた「就労支援」の商品のひとつtotonoi pizza
私にも意志があったんだ!
坂東:これまで印象的だったエピソードはありますか?
渡邉:たくさんありますね。普段あまり意見を言わない事務スタッフが、RINGOプロセスの練習で「自分にも意志があったんだ」と発言してくれた時は感動しました。
プログラムの中で「事業所の言葉」を決定する場面で、 若いスタッフが、おどおどしながらも意志決定した後から、職場でも主体的に意見を言うようになるなど、働き方が大きく変わったことを実感しました。
施設長という立場の私からすると、 スタッフが役割ごとに業務をするようになり、自然とリーダーシップを発揮するようになったのを感じています。
以前なら「どうしましょう?」と私に聞かれることが多かったのですが、今では現場の仲間で進めて、後で「RINGOプロセスを使おう」「これ、RINGOで上げよっか」と皆がすぐに言ってくれるようになりお伺いも減りました。
更には、利用者さんに言いづらいことも、以前は施設長の私に行ってきていましたが、まずは担当の職員がしっかり利用者さんと話し合うようになると、利用者さんと職員の関係性も深まっているのを感じています。
私がDXOの好きなところとして「自律しましょう」と言わないところ、があります。
最初にぬいさんからも「仕組みを整えるんだよね」と説明があったのですが、自分たちが変わることを求められるのではないことも職員にとっては、何も脅かされないという安心感がありました。
DXO導入から約2年とこれから・・・
坂東: DXO導入から約2年が経ち、現在もプログラムは継続されているのでしょうか?
渡邉: はい、月に1回程度、DXOの内容に限らず皆で話し合う定例ミーティングを続けています。
RINGOプロセスは勇気が必要な場合もあるので、練習会をたまに行ったり、支援のモヤモヤを話し合う、DXOテキストを皆で読んで感想を共有する、などの場も設けています。
3ヶ月に1回はそれぞれの仕事へのメッセージやリクエストを送り合って、仕事を振り返り、新人職員にはここに来た理由など話してもらうことで、すぐに仲間意識を持てるようにしています。
有野: 私自身の変化としては、以前は「DXO導入に失敗した社長です」なんて自嘲気味に言っていた時期もありましたが、今は「やり切って本当によかった」と感じています。
自分のことも深く探求できた時間でしたし、会社にとって何が大事なのかを感じられました。
「支援をこうしたい」と自分の気持ちを伝えられるやりがい
坂東: スタッフの方々の声も聞かせていただけますか?
渡邉: はい、直近の読書会での感想を一部ご紹介します。
40代の世話人:
「今までは決めてくれるからと考えなかったことも、DXO導入されてから意識が変わったと思う。支援をこうしたいという自分の気持ちが伝えられるようになり、自分で考えて動くようになった」
70代の世話人:
「やりがいが出てると感じてるのは、それだけ自由にさせてもらってるから。やりがいが出てきたことが、仕事を続けられてる理由です。良い会社になったと思います。」
30代の農業・職業指導員:
「蒼渓会がやっていきたい組織のあり方は、なるべく手をかけず自然に見守る農業の方法と似ていると感じます」
50代の生活支援員:
「生命体のような組織というDXOの言葉に共感し、そういう組織を心から見たいし、なりたいと願っている」
などなど・・・
坂東: 最後にDXO導入後の蒼渓会の今後の展望についてお聞かせください
有野: DXOは「終わりがある」という点が良かったです。 半年のプログラムで区切りがあり、その後は自分たちでやらなければという自立が生まれました。ぬいさんたちが毎月来ていたら、甘えてしまって、今のようには育たなかったと思います。
社会福祉法人は売上の天井が見えやすいので、売上を増やすことよりも、今いる人たちがどれだけ働きやすいか、やりがいを持って仕事ができるかという本質的な部分にDXOが合っていると感じています。
渡邉: ぬいさんたちが作ってくれた土台をこれからも大切にしながら、自分たちで自主運営を続けていきたいです。必要に応じて、これからも外部の皆さんと繋がり、相談しながら育っていきたいと思っています。
職員も組織も進化しているので、その時々に合わせたアップデートもしながら、職員が学び続け「いいなと思うあり方」を追求することも大事にしたいです。
乾: DXOは、導入すれば魔法のように全てが楽になるわけではありません。
大変なことはたくさん起こりますが、蒼渓会のお二人のように、大変なことも受け止めながら、イキイキと働くことができるようになるのがDXOの魅力です。
有野:DXO導入前は眉間にシワが寄っていたのが、シワが減って若返ったと言われるようになっていますよ(笑)
ぬいさんの存在が前に出て引っ張るだけでも、後で見てるだけでなく、一緒にいてくれるその存在の自然体なあり方が、自分自身も経営者としてのあり方としても影響してます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いかがでしたでしょうか?
今回のお話でDXOのリアルな姿を感じていただけたかと思います。
DXOが大切にしている考え方は、「組織の問題は『人』にはなく、『人と人との間』にある」ということです。
会社を変えるために「人を変えよう」とすると、変えられる側は否定されていると感じてしまいます。そうではなく、「仕組み」を整えることで、中で働く人の働き方は自然にが変わっていく、という考え方を大切にしています。
蒼渓会さんのように「RINGOプロセス」が機能するためには、これら4つのプログラムでその仕組みを整えることが重要です。
ご自身でDXOテキストを進めることも可能ですし、私たちインストーラーにご依頼いただくことも可能です。お問い合わせはこちらから。
この記事を書いた人
田中 真由 (たなか まゆ)
大企業メーカーの人事、児童福祉企業での社内統括として、16年ほど一貫して人と組織に関する仕事に携わる。多くの人に出会う中で、「その人が持つ可能性を存分に発揮できるかどうか」は本人のスキルや能力だけではなく、環境やちょっとしたきっかけが大きいと感じる。その中で、武井浩三の著書「自然経営」をきっかけに、人を変えようとしないDXOに出会う。
実際にDXOの導入現場で組織の仕組みを変えることで、人の本来の可能性が引き出される様を目の当たりにして感動し、手放す経営ラボラトリーにジョイン。
現在は、企業でのDXO導入の伴走と共に、世の中にDXOを伝える活動を行っている。
好きなことは、美術館巡り・旅・子どもの興味関心に触れること。