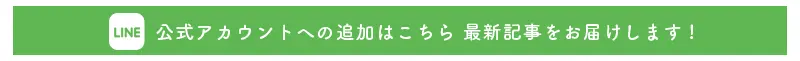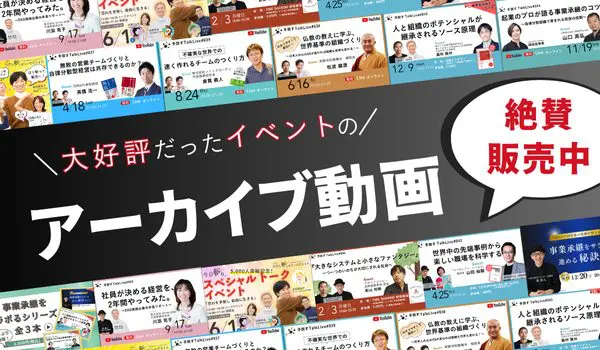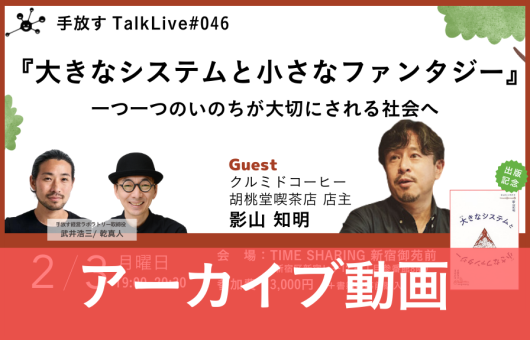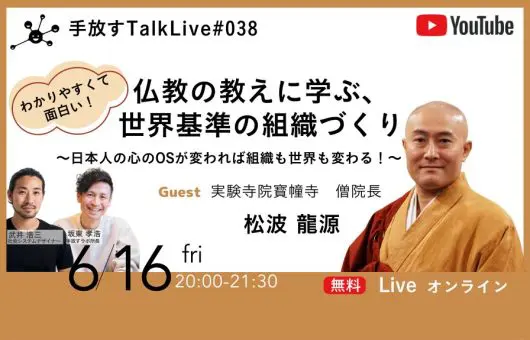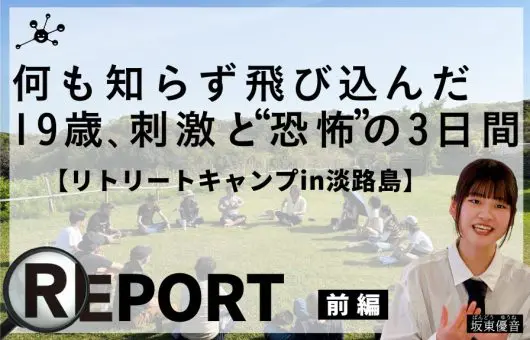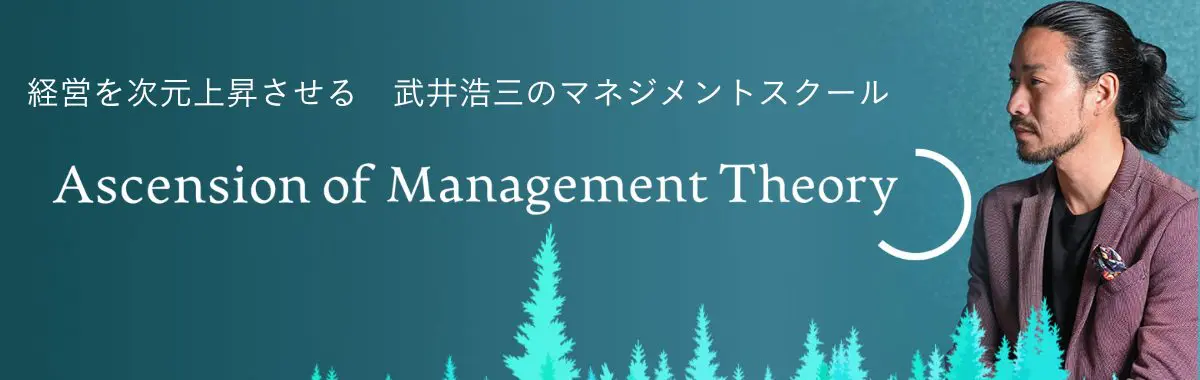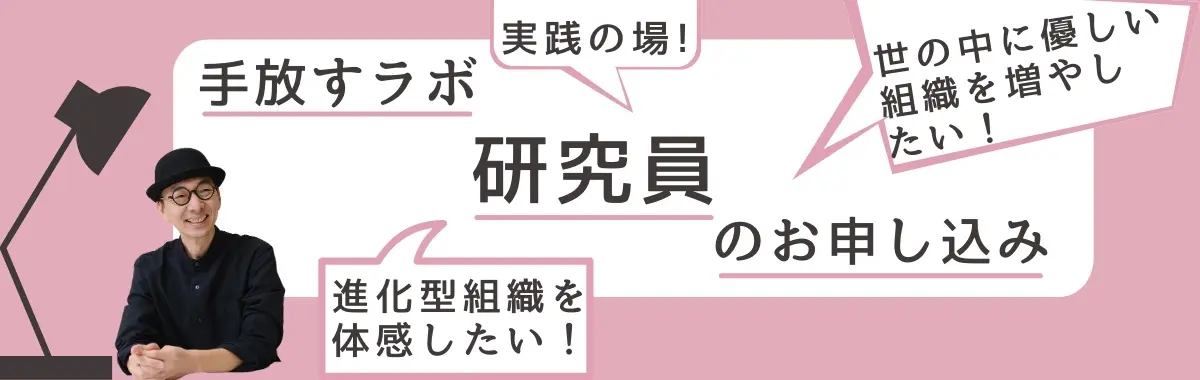組織の進化論を説いて世界的なムーブメントを起こしているベストセラー『ティール組織』。
発行部数は全世界で35万部、日本でも5万部に達している。
日本版の発行に関わり「解説」も書かれていている嘉村賢州さんを取材しました!
(※「ティール組織」の解説はこちら)
今回はラボを飛び出して嘉村賢州さんに取材に来ています。それではどうぞお聞きください。
嘉村さん、今日はよろしくお願いします。
それはやっぱ東京のほうが情報も多いしチャンスも多いしっていうとこで仕方ないと思うんですけども、私は京都が大好きだったので、何とかしたいなという思いで京都を変えようと。
しがらみだらけですし、なかなか出る杭は打たれてしまうところもありますしというところで、下は18歳から上は74歳まで、毎月約100人の市民が集まって京都の課題を考え、未来を考え、行動に移していくっていう、京都市未来まちづくり100人委員会っていう委員会を5年ぐらい事務局長でやらせていただいてまして。
そのときに比較的はじめ苦労しながらも成功していった中で、そういった技術が企業の中も紛争状態だと。M&Aで吸収合併した親会社と子会社が本当はシナジーを生みたくてくっついたんだけども、いつまでも憎しみ合っていて結局上手くいかなかった……みたいな、そういう企業内の組織風土みたいなものにもファシリテーション技術を役に立てたいというお声をいただいてそちらに入ったりとか。
で、だんだん組織風土改革・組織開発っていう分野だけじゃなくて、イノベーションとか新商品の開発、新規事業戦略とか、そういうようなものを1人の力じゃなくて組織の力でつくっていくっていうところをお手伝いするようになってきて、仕事がだんだんまちづくりからビジネスのほうが大きくなってきた中で少し問題意識を持って、3年前に一度お客さんとうちの組織のメンバー全員にすごい謝って1年間休みを取るということをしたんですね。
その休みの最中に『ティール組織』というものと運命的に出会って、稲妻が走って、探究するために海外に何度も足を運んでっていう中で探究させていただいて、これは本当に素晴らしい本だ、でも私は英語力があまりなかったので翻訳しようとは思わなかったんですけど、でも、どこが翻訳本を出すかがすごくこの日本での広がりに鍵を持つなっていうふうに思ったもので、それで著者に尋ねたんですけども。
ただ、金融の専門家の方なので、組織に関してのニュアンスとかがもしかしたらズレてる可能性もあるっていう中で、編集部にとっては渡りに船というか、私が組織の専門家だったので、しかも海外でティールのことを勉強してるのはそのときは誰ひとり居なかったので、それで「解説お願いします」ということで頼んでいただいて、それで関わらせていただいたという感じなんですね。
メンタルヘルスの問題、離職者の問題、「営業部と開発部が揉めてる」とか、「みんな当事者意識がないから何とかしてほしい」とか、そういう課題を聞いてるとほぼ共通してる。
勘で言っても当たりそうなぐらい同じ問題になっていて、ファシリテーションで入らせていただいたら喜んでもらえるんですけども、とはいえ何か矛盾というか行き詰まりを感じてたときに、根本的に人類は組織のつくり方を間違ったんじゃないかと思ったんですよ。
だから、ボタンがないスマートフォンが生まれたりとかって、携帯とかもガラッと変わってジャンプしながら進化していくんですけども、組織運営ってやっぱり人が関係してますし、すぐに結果が出るものでもないので、試行錯誤っていうのがどうしても行われにくくて、軍隊型の統率型を改善して「人は大事にする」みたいなことも入ってきてはいても、そういうところからちょっとずつ変わっているだけで、もしかしたら本当はボタン式からスマートフォンが現れたぐらいの大きな劇的な変化が組織論でもあっても良いはずなのに起こってなくて、そこに何か発明したいなっていう気持ちになってたんですね。
そういったときに、この本の原題が実は『ティール』ではなくて『Reinventing Organizations』という『組織を再発明しよう』っていう言葉だったんですよ。
全く見たことがない組織が現れる可能性があると考えてる人がいるし、実際現れはじめてるっていうことを言っているっていうことで、「これはしばらくは集中して学ぶ価値があるな」というふうに思いまして。
だいたいコンサルか広告代理店がファシリテーターを置くぐらいで、ファシリテーションで仕事にするっていうことがほとんどなかった時代なので、「なんでそれにお金を払わなければならないんだ」っていうところからやってきた。
で、だんだんとそれが仕事になりはじめてファシリテーターが広がってくると、自分の中に何が起こったかっていうと、サバイバルしてるんですよ。
すごい好奇心で、「これ学んだらもっと人が輝く」とか「組織が良くなる」「社会が良くなる」と思ってたんですけども、学ばなければ置いていかれると思いはじめますよ。
そういう自分がサバイバルモードになってる中で、その前の10年間は純粋にファシリテーションが広がったら世の中は良くなると思ってたものが、サバイバル状態になってるという自分自身も少し危ういなと思いましたし、何よりも仲間を幸せにすることが社会を変えるとかどうこうよりも一番大事だと思って生きてきた自分が、ある日職場に行って雑談してるスタッフの状況を見て「雑談が長すぎる……」と。
で、海外行くときも「一緒に行こうよ」って感じで一緒にアメリカとギリシャに行って、っていう感じで2人で進めていました、初めは。
だから、やっぱり私の周りでも「買ったけど読めない」とか、なかなか手がつかないっていう人多いんですけど、嘉村さんからの視点でのお勧めポイントというか、「こういうところをポイントにして読んだほうが良いと思うよ」というのをお聞かせいただいても良いですか?
で、ラルーさんも言ってるんですけど、「要約は読まないほうが良いですよ」と。
だから、本当に自分の固定観念とかを外して見ないと新しい世界っていうのは理解できないはずなんですけども、要約っていうのは、もしかしたらその人がオレンジ段階だったら、オレンジ段階として解釈したものとしてティールを書かれていますので。
というのも、私たちも「600ページなので、もう少しエッセンシャルなものを出したほうが良いと思うんですよ」っていうことをラルーさんに言ったんです。
そしたら、「でも気をつけたほうが良い」というようなことをおっしゃられてたんです。なので、それは本当にそうだなという。
私も何十回と読んでますけども、何十回と読めば読むほど気づきがありますよね。
今回はここまでとさせていただきます。嘉村さん、ありがとうございました。
今回のPodcastはいかがでしたか?
番組では、ご意見・ご感想・質問をお待ちしています。
ウェブサイト「手放す経営ラボラトリー」にあるフォームからお申込みください。