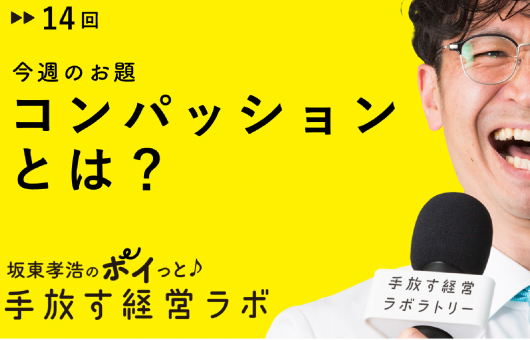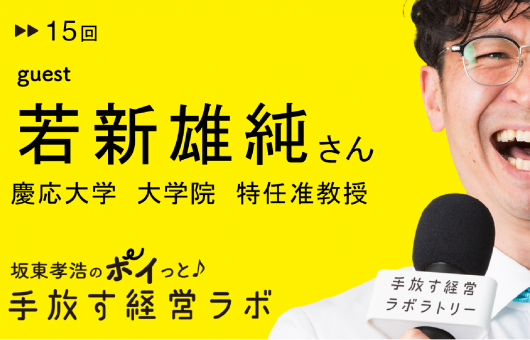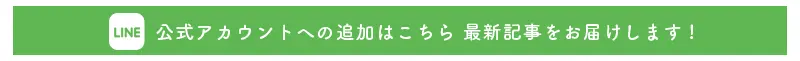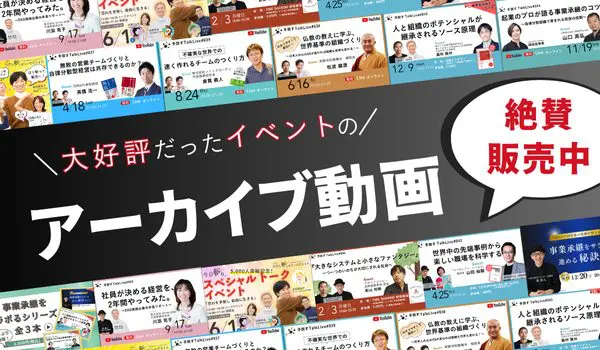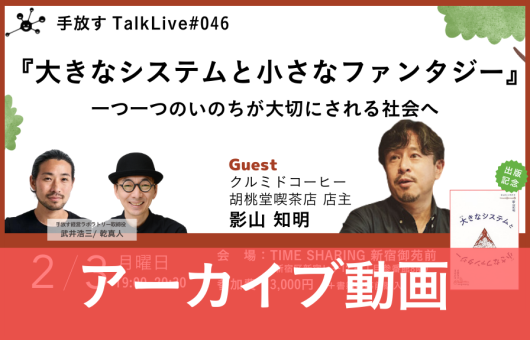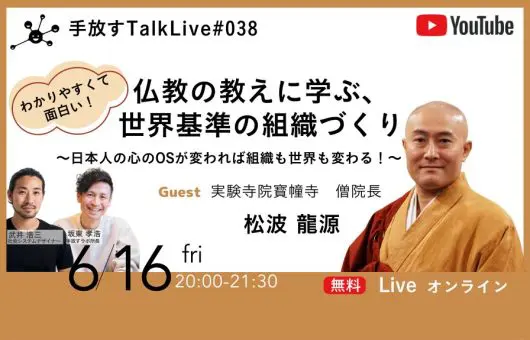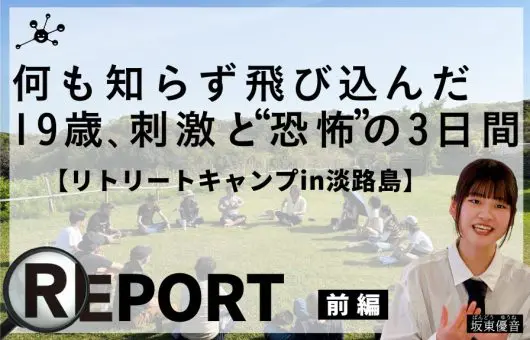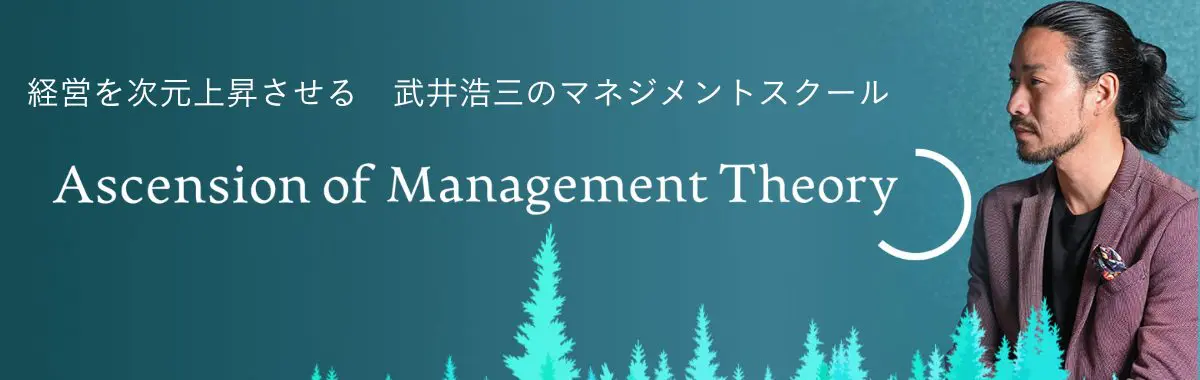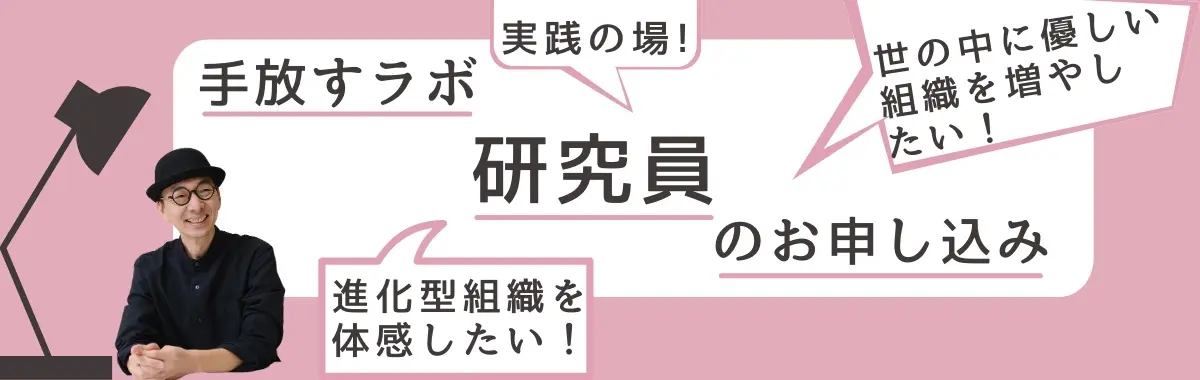多くの上司たちが悩まされている、若手社員が“張り切らない”問題。
叱られないギリギリの点数“55点”をとる若者の真意は?
若新さんの分かりやすい分析とトークに目からウロコです!
具体的に言うと、夕方ぐらいで講義が終わったら、そのあとは「次の日午後集合ね」みたいな感じで午後までは好きにして良いよという。
そのあと報告もさせなくて良いし、何やるかも自由に任せてる。任せっきりですもんね。それが新しいというか面白いなと思うんですよね。
だけど、きちっとやって帰ってくるんですもんね。それが普通の組織マネジメントの考え方すると、「新人に何もやり方教えなくて大丈夫なの?」とか、「放っといたらサボったりしないの?」って普通の人だったら考えそうなもんなんですけど、そうじゃない。
そこら辺は若新スタイルがあるなと思うんですよ。
言われてやることっていうのも、言われてでもやりたい理由が強ければやると思うんですよ。
例えば、すっげー起きるのが嫌な子に「今起きてここまで来たら2万円あげるよ」って言ったらパッと起きると思うんですよ、人から言われても。
だけど、「今起きれば2万円あげるから」って親に言われたら、「今、親戚のおじさんが来て、今起きて行けば多分1万円くれると思うよ」って言ったらパッと起きると思うんですよ。
それは人から言われることだけど、それに対する報酬のほうがもっと大きいから。
つまり、仕事を頑張れば出世できるとか、より高い給料がもらえるとか、この会社に居続けられるっていうステータスを得られるとか、それがいわゆる報酬になってたっていうことですか。
だって、マンガって1冊買ったら400円するのに、ネカフェで1,000円ぐらい払えば20冊ぐらい読めるじゃないですか、一晩かけて。
基本はそんな高くないけど、頑張った分まだ出世できたり給料上がったりしたから。
だから、それよりは、多分何やったって頑張らない人っていると思うんですけど、それはべつに無理くりはっぱかけてやらせてやったふうにしても意味ないと思うから、それよりは1人でも多く自分で「やる」って決めて自分でやって、「めちゃめちゃ良かったな」って思う人が1人でも多いことのほうが大事かなと思って。
よく会社で求めてるコミットとかじゃないんです。それは人から言われてやらされてる外的な動機なんで、コミットメントとか。本当のコミットっていうのは自分で自分に納得して決めるものだから、そういうふうに研修の中でもしてもらいたかったと。
そうなると、言われてやるんじゃなくて、本人がやりたくてやるっていうことを作るための僕の関わり方は何なんだろうなっていうことをいつも考えているってことですね。
実際にそれで外に行ってみんなやるわけなんですけども、今の若い人からしたら最もやりたくないことの1つなような気もするんですけど、それをたった数時間の講義で「やってみようかな」とか自らやりたいって思わせてるわけでしょ?
だから、やりたい人が自分で納得して、「これなら折角の機会だからやってみよう」って思って初めてできるものだと思うので、ああいう内容にしてますね。
1個は、関わり方の大きな違いで言うと、研修のあり方は僕は大きく変わってると思ってて、どんな仕事にでも古来から仕事において研修っていうのはあったと思うんですよ。
やり方は色々あるとしても、「背中見とけ」ってやり方もあるかもしれないし、秘伝の書みたいなのでまとめられてんのかもしれないし、分かんないけど。
でも、こういうときの従来の新人が研修するときの考え方は「継承」だったらしいんですよ。継承っていうのは先人が持ってるものを引き継ぐってことですね。
でも、これ、当たり前なんですけど、なんで引き継ぐ必要があったかっていうと、実は技術とか方法を記録する方法があんまりなかったかららしいんですよね。
昔はビデオとかなかったじゃないですか。
だから、継承することの重要性よりも今僕が大事だと思ってんのは、そのことよりも本人が納得して「やろうかな」っていう気持ちになっていくことのほうが大事だと思うんですよ。
だから、そんなの昔は「あ、ヤバい、今から商談だ!あれっ、どうだったっけ?」てなってパッと分かんなかったんですよ。
だから、継承していくことの重要性が結構下がってきていて。しかも継承することが貴重だった時代っていうのは継承する時間って大切な時間じゃないですか。だからみんな必死でノートとったと思うし。
そのあとビデオとか出てきたけど、ビデオだって今と違って常にVHS携帯してたわけじゃないからパッと見れないじゃないですか。
だから、そのために前半の講義でも僕が持ってるスキルを教えるとかじゃなくて、「これは僕のことだな」とか「これは僕の問題だわ」っていうふうに共感してもらうようにやってる。
ただ、55点を取る能力はあると。
それだけアジャストできる高い能力があるもんね。
だから、お互いに指とかつねり合ってるらしいんですよ。テレビの収録中だから寝たら終わりじゃないですか。でも、お互いフラフラで、ダンスレッスンして、撮影して、移動して、何々して……っていう感じで、みんな上京してる子は共同生活とかして、メイクもして、美容もやって、食べるものも我慢して、ギリギリらしいんです。
だから、自分が「やりたい」と思って、自分が「これがしたいことだ」って思ってやってるときは、どんな過酷な状況でも、それでも人権を守る程度のことはしなきゃいけないけど、それって経営者も一緒だと思うんですよ。
だから、できる限り「言われてやる」っていうものを最小限にして、「やりたいからやる」っていう割合を増やしていくっていうことができれば、根本的に働くっていうことが変わるような気がしますけどね。
今回のPodcastはいかがでしたか?
番組では、ご意見・ご感想・質問をお待ちしています。
ウェブサイト「手放す経営ラボラトリー」にあるフォームからお申込みください。