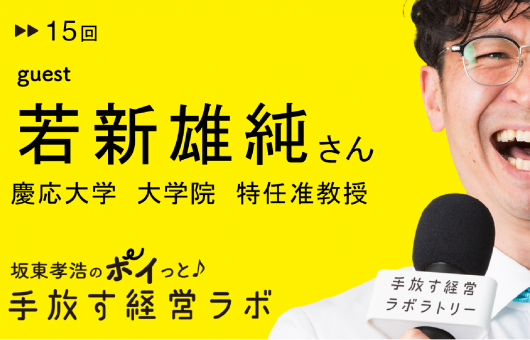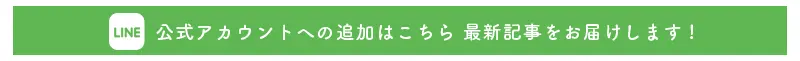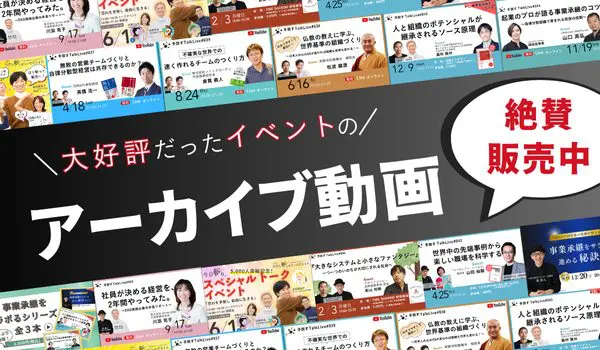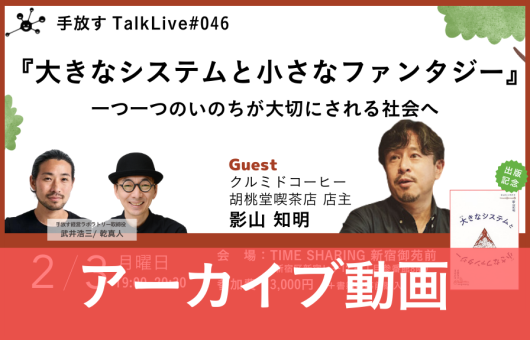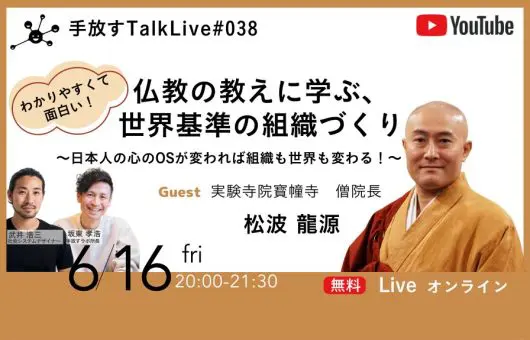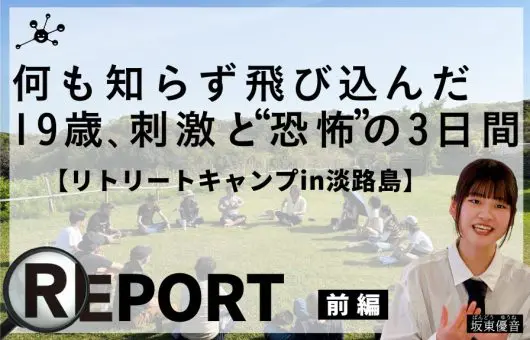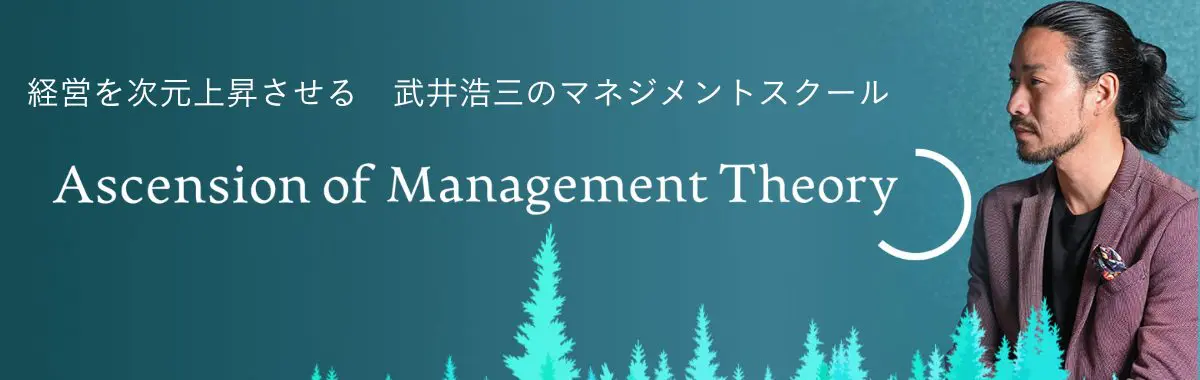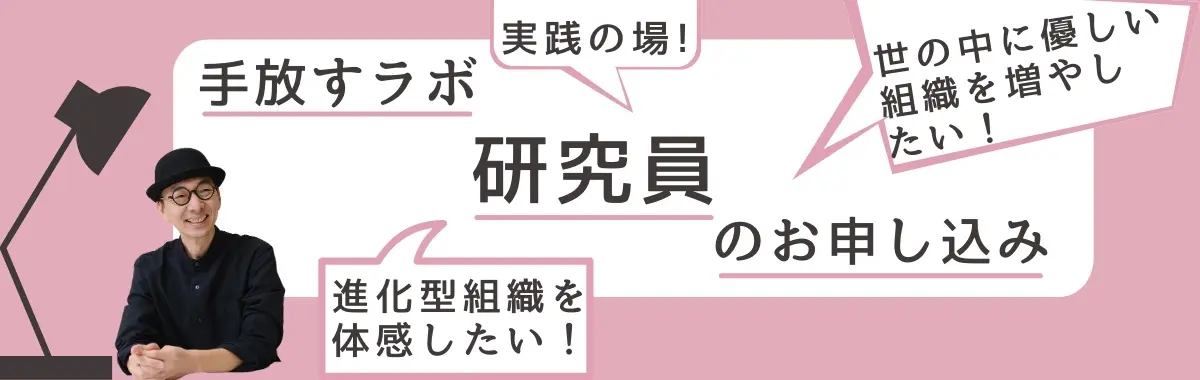第14回のテーマは【コンパッションとは?】
人に注意を与えて寄り添うという意味の、コンパッション。
コンパッションを意識することで、チームはどのように変化するのでしょうか?
そのときに、色んな要素はあるんですけど、最も因果関係があったのが心理的安全性。心理的安全性というのがチームの中に生まれてるときに最も生産性が高くなるというような調査結果になったと。で、それをリーダーがいかにつくるかっていうのが組織づくりのポイントだっていうふうにGoogleでは結論づけているということで。結構意外じゃないですか?その結果自体が。
今回のPodcastはいかがでしたか?
番組では、ご意見・ご感想・質問をお待ちしています。
ウェブサイト「手放す経営ラボラトリー」にあるフォームからお申込みください。