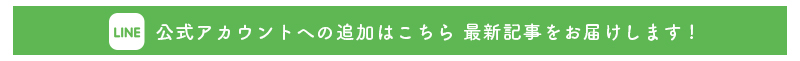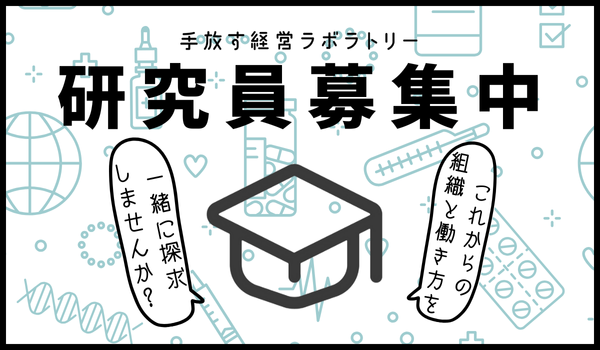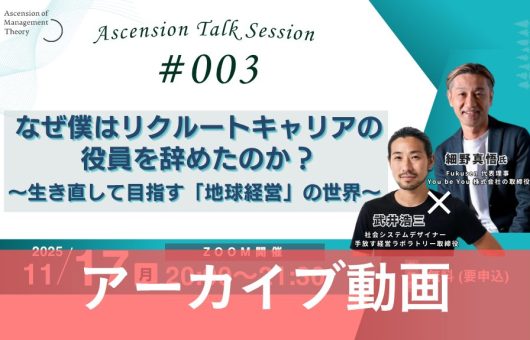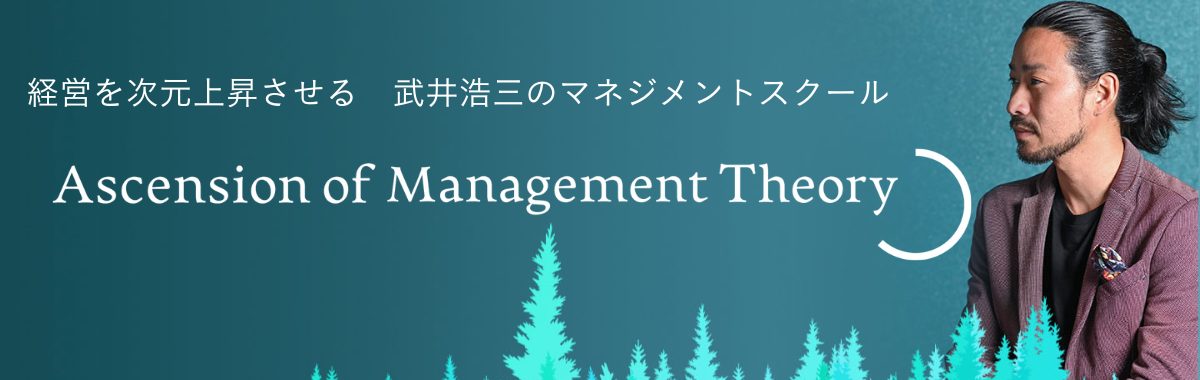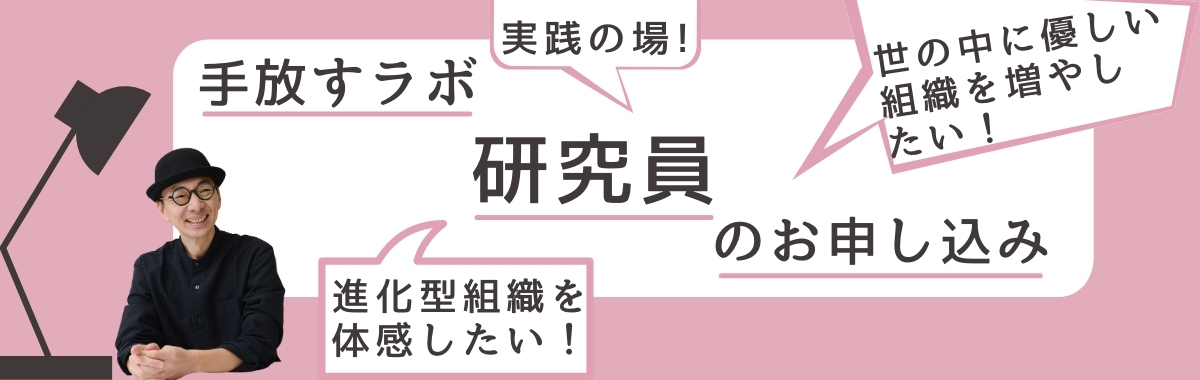2025年9月5日実施「DXOのすべてを語る夜」トークイベント

わたしの歯医者さんは、今年開業11年目を迎える埼玉県朝霞市の歯医者さんです(2025年現在)。スタッフ18名(外部委託含む)で歯の治療だけでなく予防や、お子さんからお年寄りまで生涯の健康にも力を入れている歯医者さんです。2022年12月にDXOの再起動式(DXOで、新しい組織OSでのスタートを切った日)からこれまで、そして2年半を超えた今について、リアルな変化をインタビューしました!

「わたしの歯医者さん」院長
田幡 壮さん
2014年埼玉県朝霞市に、関わる人が幸せになって欲しいと理念を掲げ、歯科医院「わたしの歯医者さん」を開業。2021年に法人化、周囲からは順調に見える反面、組織内では、新入社員が6名連続で適応障害で退職するなど、スタッフの入れ代わりが激化。
自分が目指していた真逆の状況に絶望する。
手は打つがどれも効果が出ず途方に暮れるが、「ティール組織」「進化型組織」を辿っていくさなか、「手放す経営ラボ」と出会う。これしかない!と飛び込んだ「今日斬り」にて由佐美加子さんに紐解かれ自分の中にある本当の願いを思い出す。そして組織は「DXO」を導入し、「一生ここで働きたい」と言われる組織に変容した。
2年半が経過した今も、日々、組織の進化と、自身の変容の旅路は続いている。
目次
- 1.DXO導入前、満たされない経営成長と退職
- 2.導入の不安、それでも決断した本音は「経営が嫌だった」
- 3.自分が握らなくても、やっていける!
- 4.院長からみたスタッフの変化 ー個が尊重される柔軟な働き方ー
- 5.スタッフにとっての変化 ー管理からの解放で仕事がしやすくー
- 6.院長の変化 ー全部が変わった!と言われるワケー
- 7.なくなりはしない「不安」と、生まれた「信頼できるチーム」という感覚
田幡:埼玉県朝霞市で歯科医院を経営しています。開業して11年ほど、スタッフは外部委託の方も含め18名ほどです。DXOのプログラムを導入してもうすぐ3年です。まだ3年かという感じですね。
乾:もっと経っている気がする感じなんですね。
DXOを導入しようと思ったきっかけから、改めてお教えください。
DXO導入前、満たされない経営成長と退職
田幡:DXO導入前は、経営の数字をしっかり追っていると、患者さんも増え、予約も埋まり、売上もどんどん上がって忙しくなっていました。順調に成長していたんです。
しかし、その裏側で新入社員が5人連続で適応障害で辞めてしまったんです。大体3ヶ月に1回ペースです。いじめがあったわけでもなく、むしろどうやったら新卒のメンバーが安心して学び、働けるように細かく気を遣ってやっていたつもりでした。
それでも、何をやってもうまくいかない状況が1、2年続いたので採用するのが怖くなっていました。
成長して売上も上がっているのに、全然幸せじゃない。この時に売上も1億円くらいになったんですが、この延長線上で倍の規模になったとしても、何も満たされないし、この先もっとヤバいことになる、何かがおかしいんだろうなとは思っていました。その時にティール組織などから、自然経営やDXOを知りました。
乾:この頃はフラットな状態というより、だいぶ苦しかった感じですか?
田幡:業績が上がっている時は良い感じだぞと思っていたのですが、人がついてこない、辞めていく状況に対して、何をしても上手くいかないという無力感がすごかったですね。
坂東:そんな苦しい状況で、今までと真逆の考え方であるDXO(自然経営)のテキストを読んで、「そうだよな」と思えたのはすごいですよね。
田幡:自分はそれまで、組織の稼働を優先して「人がどう当てはまるか」ということを当たり前のこととして、ヒエラルキーでやっていました。でも、DXOが個人、「一人ひとりの意志が尊重される」ことをベースにしていると知って、これだ!と思いました。
このままでは今の延長線上に進んでしまうから、自分がやっていたこととは真逆のことを逆立ちしてでもやらないと、と感じていたんです。

社長の内面を紐解く「社長今日も斬らせていただきます」〜008「業績は絶好調なのに、スタッフがwell-beingじゃない」〜
での紐解きは、再生数19,500 回超えという大反響(25年現在)↓
導入の不安、それでも決断した本音は「経営が嫌だった」
田幡:DXOの導入までは、半年ほど悩みました。
導入したらどうなるか?という絵が全く浮かばないし、失敗したらどうしようと不安でした。ぬいさん(DXOインストーラー:乾)に聞いても「わからない」と言うからどうしようかと思って(笑)
乾:僕も「やってみてどうなるかは分かりません」とお答えしていますからね。
坂東:その中でよくやりましたね!なんで、その時やろうと決められたんですか?
田幡:本当によく決められたなと、今となっては自分を褒めてあげたいです。
導入してみると、どうなるかはわからないのは本当にその通りだ、と今なら思います。
実は、導入を決めた動機はすごく不純でした。自然経営の考えに痺れたというのは本当にあったんですが、当時は「一人ひとりが生き生きとできるようにしたい」というような建前を言っていた気がします。でも、本音は、もう経営が嫌だったんです。このピラミッドの頂点に立って、一人で苦しい状況を背負うのが嫌で、「みんなに分けてやってもらったら楽だ」という思いが極まっていたんだと、今なら思います。
乾:なるほど。そんな極まった状況から解放されるかもしれないという思いがあったんですね。
田幡:やってみてダメだったら戻したらいいよね、とみんなにも言っていたし、まずやってみようという形で導入を決めました。
自分が握らなくても、やっていける!
田幡:導入後、スタッフがRINGOプロセス(DXOにおける意志決定の仕組み。意志を持った人が提案し周囲から、意見をもらって、最終的に自分が決める)を使って自分で意志決定をし、運営してくれるようになりました。お金の管理もスタッフが担うMIKANシステム(自分たちが使えるお金をリアルタイムに把握し、経費・給与や自分たちの分配を含めて管理する仕組み)を導入しました。
今までは自分が全部決めていたのに、DXOの導入中のワークショップの中で、入社たった4ヶ月のパートの方が決めてくれたということがありました。これには痺れましたね。明らかにその場ではその人が1番強い意志というかエネルギーがあったんです。その時、自分から手放せた、自分が握らなくていいんだと思えたし、本当にやっていけるんだろうなという確信になりました。
通常の社会は、忖度して考えて案を出したのにダメって言われる。そんな縦社会が当たり前になっている一方で、ここでは自分の中にあるものを場に出して受け取ってもらえる。
そんなコミュニケーションのあり方に触れて、DXOのワークショップの前半では、毎回終わるたびに「なんでこんなに豊かな気持ちになるんだろう」とメンバーのみんなも言っていました。
一方で、お金の仕組みのところは、専門職としてやってきたメンバーなので、最初は難しく感じていましたね。それでも3年やってきて自分たちでお金のことも考えているので、すごいと思いますよ。
乾:一番しんどかった新入社員の退職は、どうなりましたか?
田幡:新入社員の退職は止まりました。入ってくる人と今いる人が対等になったので、居心地の良さが違うんじゃないかと思います。
乾:以前は、いつ辞めようかと思っていたスタッフが、DXO導入後は「辞めるということが想像できないぐらい居心地の良い職場になった」と感想で言ってくれていましたもんね!
田幡:そうですね。それに、産休育休に入るスタッフが増えましたが(現在3人、昨年2人)みんな戻ってきてくれます。戻った後も、時短勤務の形態を自分で決めてくれています。
乾:それはお金を自分たちで管理していて、自分たちの人件費や会社の経営状況を理解しているからこそ、自分の働き方でどのくらいもらうかも自分で考えられるんですね。
田幡:ものすごく考えているかというよりは、肌感覚で考えてくれていると思いますね。

スタッフが意志決定してくれ「やっていけるんだろうな」と感じた瞬間
院長からみたスタッフの変化 ー個が尊重される柔軟な働き方ー
田幡:以前は、朝会とかもハキハキしないといけない空気を出していましたが、今は、みんなが自然な形で動いていて、無理に頑張らない。前は自分がみんなに和気藹々と仲が良い状態になることを課していたなと思います(笑)。今は、仲が良いかと言われると、そうでもないですが無理がなく自然になっていると思います。
仕事においては、個人の得意なことを生かして働いています。歯科助手でも、受付が得意なら受付を、中での機材管理(滅菌など)が好きならそちらを、カウンセリングが好きなら担当するなど。
以前は職種ごとに求められる業務をやって下さい、と決められた仕事をこなす必要がありましたが、今はそれぞれのスキルや想いを尊重しています。
乾:DXOのプログラムの中で、業務に対して、全員が「スキルがあるか」「元気がでるか」を点数で見える化するというものがあるんですよね。それを全員が見ると、お互いに得意なことややりたいことを踏まえて、代わるねということが起こるんですよね。
田幡:例えば、実は人と一対一で接する受付業務が苦手、というメンバーがいたので、DXO導入後は全くやらなくなりました。緊張してしまうと言う彼女に対し、周りのスタッフが役割分担を自然に考え出したんです。
乾:その方はムードメーカーだから、みんなも苦手とは全く想像してなかった。でも「-3点」までしか点数がないのに、-5点くらいつけてましたもんね。それがわかったから代われたんですよね。
田幡:やらなくなった代わりに裏方的なことや、本人が得意なところで院内の季節ごとの装飾をしてくれたり、絵を描いたりという気配りをしてくれています。
また、チームで運営していますが、チームへの参加も、個人の意志に任せています。なんか違うなと思ったら、チームから離れるということもあるし、それで全体が回るかどうかは経営チームが見て調整しています。ちなみに、人が離れがちだなというチームは、私が圧をかけているマーケティング(売る)チームじゃないかなと自覚しています(笑)。
最近、2年半経って初めて、RINGOプロセスで意志決定するスタッフも出てきました。
材料高騰の前に在庫を持っておこうと20万円の意志決定をしたり、他の院への見学のために交通費をもらう意志決定をしたりと、前はみんなのお金を1,000円でも使うのをためらっていた人が、そんな意志決定をするように変わってきたりもしています。
スタッフにとっての変化 ー管理からの解放で仕事がしやすくー
田幡:スタッフにも聞いてみると、ミーティングが重たくなくなったと言われました。ミーティングでも一人一言発言を義務付けるほど以前は発言がなかったのですが、今はそんなことをしなくても空気が重たくなく発言が増えています。
また、人を管理しなくなった、前は全て見られている気がした、とも言われました。今はチームが担当であって、何かあったらチームで対応するという体制があるから管理は必要なくなりました。
「前は、水を飲むのも全部見られている感じがした」と言われたんです(笑)。水分不足にならないように、「ちゃんと水も飲んでね」と主任が配慮で言ってくれていたことが、そんなことまで管理されるのかという印象になってしまっていたんですよね。
上が仕事を全てマネジメントしていたから、何事にも申請して実行するということが当たり前だったからですが、今は私もみんなが何をしているかわかんない状況です。
坂東:全てマネジメントしていた以前と違って、今は院長が「何の仕事してるか全くわかんない」状態なんですよね。それでも回るんですね。
田幡:回る!しかも、めちゃくちゃ効率がいい!!すごい仕組みですよね。
経費口座と自分のお金が紐づいているから、より重なりがあって、自分ごとになりやすいんですよね。チームに情報が吸い上がるようになっているから、見守るという感じです。
休暇が重なった時なども、自分たちで調整していたし、前は始末書もありましたがそんなものもなくなりました。仕事上の申請もなくなったので、仕事がしやすくなったと言われます。
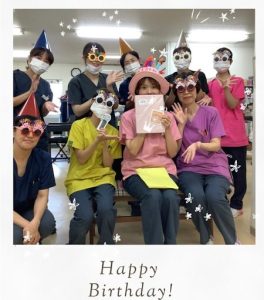
スタッフのお誕生日には小さなお誕生日会を、メンバーが中心になって開かれています
院長の変化 ー全部が変わった!と言われるワケー
田幡:経営者として、リーダーとして「こうあるべき」というのがなくなりました。なので、まずDXO導入直後は、その反動でアフロにもしましたね(笑)。
坂東:昨日まで休暇だったんですよね。これまでこんなに休んだこともなかったとか。
田幡:今回初めての長期休暇で、バリに行くのに7泊8日の休暇を取ったんです。自分がいなくて大丈夫かなという気持ちもあったんですが、罪悪感なく楽しめました。帰ってきたらスタッフにも感謝の気持ちがわいて、1人1人にハグしちゃって(3人くらいからは拒否されましたが)、スタッフからもむしろ「たまに行った方がいいですよ、柔らかくなるから」と言われました。
スタッフには、「院長は全部が変わった」「別人のようになった」とも言われています。導入前はなかったのですが、導入後には、たまに泣いたりもしました。
また「以前は何を考えているか分からなかったのが、今は素を出してくれるのが嬉しい」とも言われます。確かに悲しい、怒っている、怖い、絶望している、といった感情もすべて出すようになりました。こういう感情を出すのは、みんなのせいにしたいわけではなくて、ただ自分の中にそれがあるということを知ってほしい、という感覚です。なので今、この「素」でいられることが、本当に楽です。

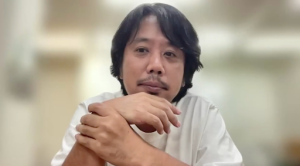
DXO導入直後は解放されてアフロにも!現在は素でいられることが楽、と語る田幡院長
なくなりはしない「不安」と、生まれた「信頼できるチーム」という感覚
田幡:導入後の今でも葛藤はあります。
私は経営全体に執着があるので、特に経費口座の運用はみんなに任せているけど、そこに葛藤もあります。「もっとお金を貯めた方がいいのでは」「もっと人を採用した方がいいのでは」といった気持ちになったりもします。そこに対して意見も伝えます。
「果たしてうまくいくのか、失敗したらどうしよう」という不安はあります。これはDXO導入前も不安だったし、導入後も不安がなくなるわけではないんですよね。不安であることは変わらずですが、DXOと関係なく不安や恐れは考え方の癖でありその人のエゴでしかないなとも認識しています。
乾:導入に踏み切るのが怖いと思っている経営者の方に、今の田幡さんから当時の田幡さんに声をかけるとしたら?
田幡:「怖いよねって。マジで。そりゃそうだ!」と共感します。
だけど、「どうしたいの?」と聞きますね。恐れや不安がブレーキになっているけれど、アクセルを踏みたいから迷っているんでしょう、と。
不安や怖さはなくならないものです。苦しんでいるということは、経営したいということなのだから、やりたいならやったらいい。
乾:気持ちの面とは別に、DXOを入れたことでの課題はありますか?
田幡:小さいことで気になる時もありますが、DXOの仕組み自体に正解はないものだと思っています。
お金の仕組み(MIKANシステム)には課題感も持っています。業態によって準備する必要もあるなと。
例えば業態によっては、機材の故障などでいきなり100万、200万円といった大きな支出が必要になることもありますよね。経費口座を四半期ごとに1/4ずつ分配してしまうと、枯渇する可能性もある気がします。なので、1/4の分配ではなく1/8とするなど、業態によりプールしておくお金の幅の設定は必要かもしれないなとは感じています。
でも、全て経費口座も自分たちで管理してくれているんですよね。昇給など、私としてはみんなの給与をどうするかということは一番考えたくないことなのですが、自分たちで話し合って決めてくれるというのは本当に楽ですね。
以前実際に経費口座が枯渇し、給料が出なくなったことがありましたが、スタッフが話し合い、給料日を遅らせるなど自分たちで調整して解決しました。私としては一番見たくなかった状況だったのですが、スタッフがなんとかするのだと分かりました。
坂東:その時スタッフの人は「どうするんですか?」ってならなかったんですか?
田幡:なりませんでした。私としては「半年前から言ってたじゃん!」と思ったし、見たくない状況でした。そうなったら、みんなが「DXOがやっぱり嫌だ」とか「自分が責められるのでは?」とも思っていたんですが、全くそんなことにはなりませんでした。
自分ごとになっているし、ならざるをえない仕組みなんですよね。
乾:最後に、参加者の方からの質問です。
DXOを導入して、スタッフとの共同体感覚は出てきましたか?
田幡:私は、めちゃめちゃありますよ!
以前は自分から分離しがちで孤独を感じていましたが、今はみんなで会社を運営している感覚があります。スタッフからもめちゃくちゃ愛されているし、気にしてくれているというのを感じているし、信頼できるチーム、共同体という感じです。
言いたいことが言い合える、居心地がいいところでいられるというのは大切にしたいです。
DXOは仕組みがあるから、純粋に「自分がどうありたいか」だけで人との関係性を作っていける。自分次第でどうにでもなっていく仕組みだと思います。
——————————————————————————–
いかがでしたでしょうか?
DXO(ディクソー)とは?
DXOは、「人が人らしく働ける組織」を探究するプログラムです。
組織の問題は人ではなく、人と人の間にあるという考え方を大切にしています。人に直接アプローチするのではなく、仕組みを整えることで人が自然に変わっていくという手法を取っています。
<仕組みの例>
- 言葉(存在意義)の整理: 従来トップダウンだった経営理念的な言葉を、現場が意志決定する時の判断基準となる
- 役割分担の整理: 会社の機能を整理し「売るチーム」「作るチーム」など目的に沿ったチーム担当制を作る
- お金の仕組みの整理: スタッフが管理するお金の範囲と設定方法を整理する
- 情報の見える化: 経営者と同じ視座で判断できるよう、情報共有の仕組みを整える
一律の正解はなく、組織ごとに最適な仕組みを一緒に考えます。
自社の場合はどんな進め方ができるのか、実際のプログラムはどんなものなのか、
聞いてみたい方は、ぜひ一度ご相談下さい。
個別相談(無料)のお申し込みはこちら
この記事を書いた人
田中 真由 (たなか まゆ)

大企業メーカーの人事、児童福祉企業での社内統括として、16年ほど一貫して人と組織に関する仕事に携わる。多くの人に出会う中で、「その人が持つ可能性を存分に発揮できるかどうか」は本人のスキルや能力だけではなく、環境やちょっとしたきっかけが大きいと感じる。その中で、武井浩三の著書「自然経営」をきっかけに、人を変えようとしないDXOに出会う。
実際にDXOの導入現場で組織の仕組みを変えることで、人の本来の可能性が引き出される様を目の当たりにして感動し、手放す経営ラボラトリーにジョイン。
現在は、企業でのDXO導入の伴走と共に、世の中にDXOを伝える活動を行っている。
好きなことは、美術館巡り・旅・子どもの興味関心に触れること。