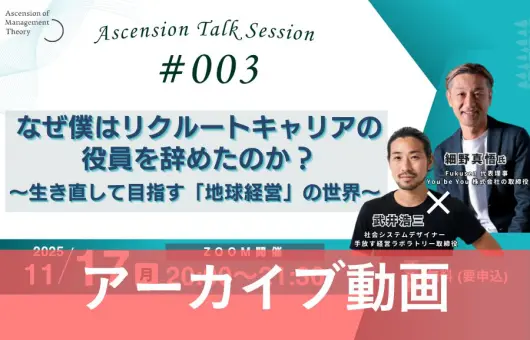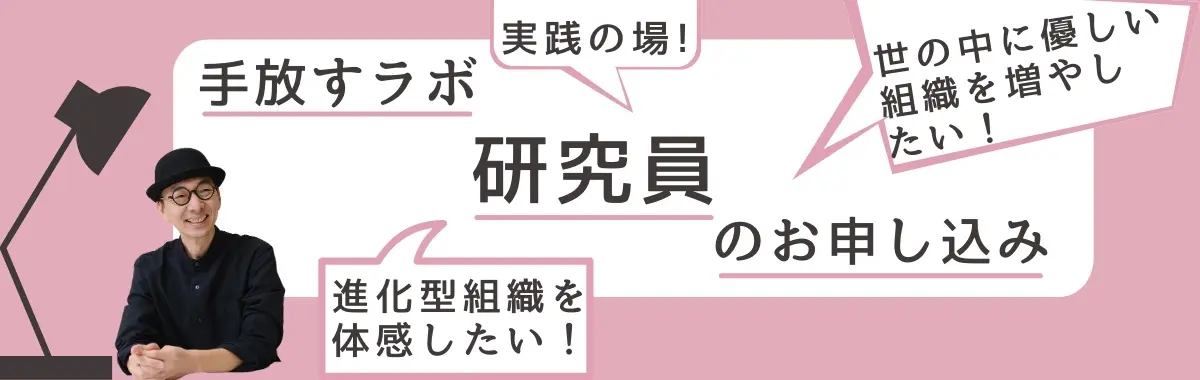「HRアワード 2018」優秀賞
「読者が選ぶビジネス書グランプリ 2019」マネジメント部門
「ITエンジニアに読んでほしい! 技術書・ビジネス書 大賞 2019」ベスト10
組織論をテーマとしたビジネス書としては異例の7万部突破!大ヒットとなった「ティール組織」。
(※「ティール組織」の解説はこちら)
その出版を手がけた英治出版株式会社も、ユニークな組織づくりをされています。
「あまり組織を大きくする気がない。社員の人数を必要以上に増やさないようにがんばっている。」
「応募者が履歴書を送ってきたら不採用」
社長の原田英治さんに、英治出版を立ち上げた経緯や、組織づくりで大切にしている考え方をお聞きしていきます。
■原田 英治さん プロフィール
英治出版株式会社 代表取締役。1966年、埼玉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、外資系コンサルティング会社を経て、1999年に英治出版を共同創業。創業時から「誰かの夢を応援すると、自分の夢が前進する」をモットーに、応援ビジネスとして出版業をおこなっている。2018年から「親子島留学」を利用し、1年半、東京と島根県隠岐郡海士町の二拠点生活を送っていた。
坂東:皆さんこんにちは坂東孝浩です。今回も英治出版株式会社の代表取締役原田英治さんをゲストにお迎えしてお送りします。原田さん宜しくお願いします。
原田:お願いします。
坂東:前回は英治出版を作るまでの話がとても面白かったんですが、今回は実際にどのように作っていったかを伺いたいと思います。作る際に「起業創造力」という本を参考にされたと…
原田:そうですね。2つ参考にした本があって、どちらも親の会社時代にプロデュースした本なんですけど。企業創造力は、いかに企業の中に創造力が生まれるのか。著者が教育学の先生なので、そもそも創造力を教えることができるのかという。教えたら創造力じゃないじゃんという問いからスタートしていて、いろんな企業で創造力ができる研究をしたところ、6つ位のその創造力が生まれやすい環境作ることができるということを参考にしました。自分自身も創造力は非常に大事だと思ってるんですが、そしてもう1つは、「起業家の本質」というタイトルで英治出版に残ってるものがあって、これはアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーを受賞したウィルソン・ハーレルという著者がこれを書いてるんですけど。起業家はリスクを犯さないと。リスクがリスクでなくなるまで創造力をくわえ続けるのだと。例えば起業家が綱渡りをしてるように見えても、起業家はリスクを排除してるから一本道を渡っているようなものだと。同時にリスクを排除できなかった時に、やらない自由を持っているのが起業家だと。だから起業家はリスクを犯さないためにいうのが、納得できるというか。リスクに創造力を加え続けるってのも大好きだし、また創造力は人からも借りられるんですよ。
坂東:自分の中だけでなくてですね。
原田:起業創造力でクリエイティビティーの本質を言い当てているのが、結局入社して数年経つと組織の事がよくわかってくるので、組織の中で大きなクリエイティビティが発揮される時に、実は誰がどのような創造力を発揮するかわからないっていうことがわかってきた。
坂東:予測もできないし、意図的にも起こせないし。
原田:ただ起こった時には、そのパワーは絶大であると。誰がどんなことで起こすかはわからないし、起こるかどうかもわからない。
そういうものだと。
坂東:本の中でも努力した分、現実に報われないかもしれないけど…と書かれていたのが面白いなと思って。
原田:自分の中で環境を高め、そしてみんなの創造力を自分たちが立ち向かうリスクに対して加え続け、そしてそのリスクが排除できなかった時には、僕らはやらない自由を持っているということが自分の経営観でありますね。英治出版がこういう会社であったらいいなと。
坂東:前回もありましたが、社員に幸せであって欲しいということはとても大事だと。
原田:やらない自由を持っているという事に通じるかもしれませんが、無理してやって欲しくない。さらにその夢とか創造力で世界観が広がるし、また何かそれを実現しようと思って努力すれば深まってより細部まで創造できるような。実現性が高まり幸せも大きくなると思うんですよね。
坂東:実際にそういう考えで組織づくりに落とし込んでいく時に、どんな事をされたんですか?
原田:企画会議なんかが顕著かもしれないです。プロデューサーが企画を提案して、みんなでやりたいという前提でフィードバックしていくわけですね。全員から拍手が起こる時が決まるという時で。著者の情熱を受け取ったプロデューサーがみんなにこの企画をやりたいと思うんだけどどうだろうかみたいな形で提案するという事です。やりたいことありきですね。
坂東:でもやりたいからとプロデューサーが押し通せるわけでもないと?
原田:今すぐやりたいからいいですよってことじゃなくて、なんでやりたいか、その著者が何をしようとしているのかっていう、やっぱりみんなも納得する時間だったりみんなのアイディアをそこに提案するし、フィードバックする時間だったりそういう間合いが必要で。
だから外部の人がうちの企画会議を見ていて、そこまで話が詰まったのだから、そろそろ拍手してもらえるかどうかの承認を得たりしないんですかっていう話をすることがあると思うんですけど、うちは承認を得るんじゃなくて、相撲の立ち会いに似てる様な、呼吸が整った時に拍手が起こるっていった方がより正確な気がしていて。
坂東:じゃあ、決を取りましょうではないんですね。それはすごい。
原田:株主総会で拍手をもって賛成の意をなたいな感じではなく、行事的に誰かが、まーそろそろと言う事もあるんですが、基本的にはみんなそれぞれが、大体この企画について納得感を持てたし、自分がプロデューサーに十分フィードバックはしたな、そしてその著者の情熱を受け取ったプロデューサーがこの企画を今後進行して行く準備がだいぶできただろうと思えた瞬間に拍手が起きると言ったほうが正確なのかな。
坂東:その空気感、パラダイムは独特ですね。
原田:独特でしょうね。だから企画会議は沈黙も多いですよ。
沈黙の時間に、多分それぞれの中で自分自身分にフィードバックしたかとか、この企画にもう賛成って言えるのかということも含めて、内省してたりするんじゃないのかな…。
論理的というよりも、最後は自分の気持ちが納得しているかどうかが問われていて、そこで自然とみんなの拍手が揃う時に企画が決まります。
坂東:面白い。そういうのは入って間もない人いたり、社員にもそれぞれ差があると思うんですが。
原田:だからもう早くに拍手してもいいと思ってる段階の人も、いると思うんですけど、ただ周りがまだ質問だったり、フィードバックを続けていると、空気感がまだなのかなと思ってるんじゃないかな。僕自身もこの企画は、前から聞いていた応援したい企画だし、すぐにでも拍手してもいいんだけどと思う事はあるんですが、やっぱり周りのメンバーがそこのフィードバックをすることによって、よりそのプロデューサーが準備ができたりとか、
違う視点をそこで得られたりしているので、学びの場になっていますね。
一連のプロセスが大事で、みんなの満足度や納得度が高まる間を待っています。
坂東:納得度をすごく大事にされているんですね。
原田:納得度。納得度しかないのかもしれません。企画の製品はわかんないですよね。この本出したら絶対儲かるっていう商売だったら、そんな楽な商売ないですよね。出版しても儲からない本を作ってしまうこともあるので、もうみんながこの著者を応援したいかだとか、納得して出せるしかないです。納得して出せるための準備が整っているかが結構大事ですね。
坂東:今、著者を応援したいかどうかという話が出ましたが、それが結構大事な会社の方針としてあるんですね。
原田:経営信念にもあるんですが、誰かの夢を応援すると自分の夢が前進するというのを掲げて、著者応援する出版社でありたいというのが1番大きいかもしれません。
坂東:本が売れるかどうかというという単純な事ではなくて
原田:本は著者を応援する道具のようなもので、売れるって言ってるのも、未来を含めて今のマーケットで売るのか、単純に現在のマーケットだけ見ていては商売できないような気もするし。僕はどっちかって言うとその著者がこれからどうなりたいとか、単行本というメディアが歴史の中に残していくようなものだと思っているので、未来にも読者がいるかとか、そういう観点で応援できたらなぁと思ってますけどね。
坂東:基本的には絶版にはしないと。
原田:絶版にはしたくないですね。ただまぁこれも一理じゃなくて著者を応援するために、単行本が良いと言う形で出したけど、それが情報として古くなれば、改訂するなり絶版にするなり、そういう事は起こり得る事はしょうがないかなと思っていますけどね。役割を終える本はあり得ると思いますけどできれば絶版にしない本を作りたいなと。
著者を応援したいか、したくないかという話だから、ボツ企画はないんですよね。この著者を応援したくないっていう拒否権みないなものがあるとすれば、社長にはである僕にはあるとは言ってるんですけど、基本的にそれが発動されることがなくて、みんなでフィードバックをして企画していたプロデューサーが何か違うと、単行本で応援する形ではなかったり、この著者の言ってることっていうのが自分たちでまだしっくりこないってなると、そのプロデューサーが諦めた時がその企画がなくなる時であって。企画会議でこの企画はボツ企画ですと決める事はないですね。
坂東:なるほどね。プロデューサーの判断に委ねられますね。
原田:そういう意味ではティールではセルフマネジメントに近いですよね。支援するアドバイスシステムだったり、フィードバックシステムになっているのが企画会議ですね。
坂東:さっきのやらない自由があるのと繋がりますね。
原田:そうですね。自分自身が出した提案であってもリスクが排除できなかった時には、そのリスクが他のメンバーから提示されることもあって、それに気づける事もありますよね。その時に気づいたリスクを、更にみんなの創造力を加えても排除できなかった時には僕らはみんなやらない自由をもっていると。
坂東:いかに本にするのではなく、著者を応援したいかどうかで、コンテンツを単行本にして応援しようと思えた時にやろうと。
原田:そうですね。うちは著者にこういうターゲットに対してのメッセージにした方がもっと幅広い読者層になりますよみたいな事は、ほぼほぼ言わないです。たくさん売れますよって事は重要ではなくて、絞れば絞るほど1人の読者を想像してくださいと。それはあなたが届けたい1人の読者がいるならばその読者と同じ人は未来にも現れるはずだから、あなたが活動を続ける限りそのほうが売れ続けますねっていうスタンスなんですよね。
坂東:なるほどね。一貫性がありますね。
原田:一貫性というか、そういう形で応援したいなと。僕たちは大きな出版社ではないので、ますに情報を流したり、広告してブームを作るのが得意な出版社ではないと思うので、著者を応援して、著者の仲間からその直接一人ひとりにいっていうか、ネットワークの階層を1段1段降りていくように、口から口へというか、友達の友達はみな友達みたいな理論で。そういう形で広まっていくのが重要だと思ってるし、著者もそういう形で開拓されていく事を望んでいるんで。だからSix Degrees of Separation という六次の隔たりで全人類が繋がっちゃうっていう考え方は、英治出版では重要な考え方で、ネットワークの階層を使うと言ったら語弊があるけど、そこを降りて行くためには直接繋がっている目の前の相手を大切にすることが次の階層につながる唯一の方法だと思うので、だから誰かの夢を応援すると自分の夢が前進するというのは、その階層を使っていずれまた、社会を巡って自分たちの夢が押し上げられるようなイメージですね。ギブアンドテイクで夢が叶うっていっている訳ではないんですよ。
坂東:なるほど、なるほど、面白いですね。
次回は、会社を大きくしたくないといういう事について、掘り下げて伺いたいと思います。
原田さん、ありがとうございました。
原田:ありがとうございました。
Spotifyはこちら